東京葬儀式社ファイナルプロデュースへご一報ください
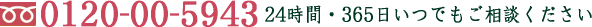
お亡くなりになったその日から、お通夜、お葬式まで、すべてのことを、
堀ノ内斎場の中で執り行えます。
御安置もできますので、ご自宅でのご葬儀が執り行えないような場合でも、
安心して搬送ができます。
東京葬儀式社ファイナルプロデュースは、元ホテルマンの気持ちのこもったサービスいたします。
ご遺族の気持ちに沿った、思いやりの葬儀をモットーとしており、
お客様には満足度99%をいただきました。
ご葬儀の費用についてもご心配がおありかと思いますが、
わかりやすいプランにて、無駄を省き費用を抑えます。
その中で、大切な故人様を送るための心を込めてサポートさせていただきます。
プランの内容を詳しく知りたいという場合には、下記よりご覧ください。
⇒堀ノ内斎場 ご葬儀プランはこちらです。
堀ノ内斎場は、地下鉄丸の内線の新高円寺で、1・2番出口より出ていただきますと、
歩いて8分ほどで到着できます。
ご親族がお越しの際にも、わかりやすいとの声をいただいております。
]]>