‘お葬式の基礎知識’
弔電を打つ場合
訃報が届いたにもかかわらず、すぐ弔問できない、という場合。
お悔やみの手紙を書くのではなく、弔電を打つという方法もあります。
弔電を打つ時には、
「115」(局番なし)に電話を掛ける方法
NTTの支店や営業所に出向く方法
また、インターネット(NTTのD-MAIL)があげられます。
支店に出向く場合には、営業時間内にうつ必要があります。
電話の場合は午前8時~午後10時までに申し込みます。
インターネットの場合は24時間いつでも申し込めます。
どのようなメッセージがいいのか、と悩む場合には、
弔電用の文例を選ぶとよいでしょう。
また、自分で心をこめて作るのも良いでしょう。
弔電は告別式で読む場合がありますので、
必ずあなた(発信人)の名前を通信文の終わりに入れるようにします。
宛名は喪主です。もしわからない場合は「故●●様 ご遺族様」という形にします。
送り先は自宅か斎場です。
葬儀の前日までには届くようにします。
電話で打つ場合には、
あらかじめ打つ内容を考え、相手の住所やお名前をメモしたものを用意します。
そして、115に電話をします。
オペレーターに自分の電話番号と名前を伝えた後、
相手の住所とお名前を伝えます。
その後、電文をゆっくりと読み上げます。
漢字、ひらがな、などもしっかり伝えましょう。
発信人の名前を入れたいときには続けて、名前を伝えます。
最後にオペレーターが、相手の住所、お名前、電文を復唱するので、
確認して終了です。
お悔やみ状を書くときに留意すること
訃報を受けたときにすぐに弔問できない。
そういう事情がある場合には、弔慰のお手紙を書きましょう。
または、弔電を打っておき、あとから改めてお悔やみのお手紙を書くという方法もあります。
電子郵便(レタックス)を使うことで、心のこもった手書きの手紙を届けることもできます。
こちらは弔事用の封筒に入れて届けてくれる点がお勧めです。
お悔やみ状には以下の内容を書きましょう。
・なくなったお知らせについての驚き、悲しみ
・故人の人柄を偲んで、死を惜しむ
・告別式に参列できない旨とその理由
・同封した香典をご霊前に供えてほしい、とのお願いの言葉
・遺族の気持ちに立ち、慰めや励ましの一言
・故人の冥福を祈る一言
さて、お悔やみの手紙を書くときにはいくつか留意点がありますのでお話します。
まず、喪主があなたの目下の人、親しい友人であったとしても、
言葉づかいは丁寧にし、心を込めて書きましょう。
季節のあいさつは省略して、弔慰の言葉から書き始めます。
結語は敬具としましょう。(草々は、言葉が重なるため不向きです)
自分の今現在については書かないようにしましょう。
遺族の気持ちを図り、丁寧な文章、言葉づかいをする必要があります。
感情的な文章にならないよう心がけます。
死、という言葉を使わず、隠れた、逝ったという言葉に置き換えます。
香典を郵送するとき
訃報を受けた際、遠方に住んでいたり、どうしても弔問できない事情がある場合があります。
そのようなときには、できるだけ早いうちに香典を郵送するとよいでしょう。
その際は、香典は不祝儀袋にいれ、現金書留にておくります。
香典袋には、実際に持参するときと同じように表書きをします。
相手の宗教がよくわからない場合には、「ご霊前」と書きましょう。
不祝儀袋は白地のもの、また水引が印刷されているタイプのものでも
構いません。
中袋には、住所、氏名、いれた金額を必ず書きましょう。
現金書留の封筒に住所を書いてあるから、と
省いてしまうのは避けましょう。
あとで遺族がお香典の整理をする際に、困るからです。
香典には簡単なお悔やみの言葉と、
参列できないことについてのお詫びの手紙を添えて送るとよいでしょう。
会社関係者の訃報を受けたとき
会社関係の方、同僚や上司、部下、それから取引先の相手の訃報を受けることも
有るかと思います。
その時には、まずは会社という組織の中の一員として、
行動するように会いましょう。
故人と親しくしていた時にも、
先に一人で弔問することは控えた方がよいです。
例えば、会社での葬儀関連の担当部署があると思います。
そちらの方針に従うようにしましょう。
手伝いとして指名された場合には積極的に引き受け、
香典の金額、供物についても、取り決めどおりにしていくようにします。
もし、故人と特に親しくお付き合いしていた間柄だった場合で、
先にプライベートで弔問をしたいという場合は、
上司にその旨を話して、了解してもらってからうかがうことをおすすめします。
亡くなったという連絡を受けたとき -近隣の方の場合
もし、亡くなられた人が近所の方で、そして、親しくしていた場合は、
すぐに弔問しましょう。
そして、必要ならばお手伝いを申し出るとよいでしょう。
例えば、買い物が必要あったり、台所関係のお手伝いで
人手が足りない場合もあります。
そういった、雑事を引き受けてあげるといいと思います。
葬儀の進行には立ち入らないのがマナーです。
例えば、食器や湯飲みを洗ったり、
座布団を用意する、暖房器具を提供する、など
あなたにできることをお手伝いするようにしましょう。
近所に住んでいながら、特に親しくなかった場合には、
玄関先でお悔やみを述べておき、
後日、通夜か告別式に参列しましょう。
住んでいる地域によっては、
町内会などで決められた役割がある場合もあります。
その時にはそちらの方針に従うようにします。
亡くなったという連絡を受けたとき -友人・知人の場合
故人と親しい友人、知人であった場合
連絡を受けたらすぐに駆けつけましょう。
服装は、普段通りのものでも構いません。
そして、人手が足りない様子でしたらお手伝いを申し出るとよいでしょう。
もし、故人とはそれほど親しくなかった場合には、通夜、告別式、
どちらか一方に出かけるようにします。
遺族からの連絡に、すぐ駆けつけた場合、
玄関先でお悔やみを述べ
「お通夜のときに、あらためて伺います」という形で挨拶をしてから
帰っても構いません。
もし、遺体が安置してある部屋へ案内された場合には、
お線香をあげたあと、遺族にお悔やみの言葉を述べましょう。
長居はしないようにするのが基本です。
亡くなられたご本人がどのような交友関係を持っていたのか、
遺族がわからないことがよくあります。
もしあなたが故人と特に親しい間柄だったのでしたら、
友人、知人への連絡を担当して差し上げると、遺族に喜ばれます。
亡くなったという連絡を受けたとき -近親者の場合
近親者がなくなった、という連絡を受けた場合は、とにかく、すぐに駆けつけましょう。
着いたらすぐ、遺族にお悔やみを述べます。
そして「お手伝いできることはありませんか?」と聞いてみましょう。
遺族は、大切な方が亡くなられた悲しみ、そして
闘病後に旅立たれた場合には看病で疲れてしまって、
気持ちの上でも沈んでいる場合が多いです。
そんなときにこそ、
近親のものの手助けが大切ではないでしょうか。
服装は最初のうちは喪服である必要はありません。
動きやすい、サッと小回りの利く服装が望ましいです。
男性ならば受付、式場のかかり、
女性ならば、台所関係のお仕事や弔問客へのお茶出しなどの接待を引き受けるとよいでしょう。
もし、そのまま喪家で手伝うという時には、
葬儀までに喪服を用意してもってきてもらうよう、自分の家族に話しておくようにします。
もし、遠方に住んでいた場合は、
さっと駆けつけることは難しいかもしれません。
その時には、連絡を受けたときにすぐ、
簡単なお悔やみの言葉を述べます。
そして、数日分の支度をして出向きます。
出発する前には、何日の何時ごろ到着するのかということを知らせておくとよいです。
そして喪服は持参しましょう。
危篤の知らせを受けたとき 参列側の心得
ご親戚、ご友人、知人が危篤、・・・との知らせ。
そんな時には、とにかく「できるだけ」急いで、駆けつけるようにしましょう。
危篤の知らせをいただいたということは、
亡くなる前に、会わせたい、と家族が願ったということなのです。
このような知らせをいただくと、
つい気が動転してしまいがちですが、冷静になって確認しましょう。
どこに行けばいいのかということを知らなければ、駆けつけることができませんから。
自宅なのか、病院なのか。
もし病院でしたら、どこにある病院なのか。
それだけでなく、病室の番号や病院電話番号なども聞いておくとよいでしょう。
駆けつけるときの服装は、今着ている服装のままでも失礼ではありません。
職場の服装、普段着でもいいのです。
とにかくできるだけ早く、訪れましょう。
もしも、知らせを受けたとき、遠くに住んでいた場合。
どうしたらいいのでしょうか?
駆けつけた先で、は滞在する可能性があります。
万が一、ということも考えて、喪服や靴などの用意も必要となるでしょう。
ですが、亡くなることを予感したかのように用意していくということは、
先方はあまり気持ちの良いものではないと思います。
そのような時は、駅の手荷物預かりやコインロッカーに預ける、
または、万が一の時に後からくる人に荷物をお願いしておく、などの配慮が必要になります。
喪主と施主の違いとは
お葬式の用語の中で、「喪主」と「施主」というものがあります。
どちらも「主」がつき、お葬式を行う側の方だということは想像がつきますが、
実際、どのような違いがあるのでしょうか?
今日はこの点についてお話します。
喪主は、ご遺族の代表。
葬儀を執り行うのが役目です。
弔問客の対応などをする必要もありますから、通夜までに、誰がやるのかを決定しておきます。
喪主は基本的には、故人と一番血縁が近い人が務めます。たいていは、配偶者、または子供が行います。
昔からの習わしとしては、親にあたる人は喪主は務めませんでした。(逆縁と言います)
また故人の配偶者が女性の場合は、後継ぎの長男がなりました。
ですが現在は、この点はあまりこだわらないケースが多いです。
喪主は葬儀の代表、という形的なものになっているともいえます。
では、施主とはなんでしょうか?
あまり聞いたことがない、とお思いかもしれませんね。
ですが、施主もお葬式、法要には大切な役割があります。
施主=布施をする主 ということで、つまり、葬儀に掛かる費用を賄う人です。
法要の場合も儀式の運営責任を負います。
一般的には喪主と施主は同じ人が行います。
葬儀社選び 打ち合わせ
お葬式について、事前にご準備しておくことで
もしもの時にあわてずに対応できます。
大切な人がなくなると、どうしても気持ちの上で負担が大きくなります。
そのためにも、事前に知っておくこと準備しておくことをお勧めしています。
葬儀社を選ぶときにも、いくつかの葬儀社を比較して判断するとよいのではないでしょうか
まず、インターネットで葬儀社を探した際には、
メールの返信の内容が丁寧かどうか、
また、電話対応でもその葬儀社がどのようなところか、個性が見えることと思います。
また葬祭ディレクターがいるかどうかも大切です。
電話で問い合わせるだけでなく、一度足を運んでみてもよいでしょう。
しっかりと店舗を持っている会社かどうかを確認するという意味もあります。
対応は誠実でしょうか?
サービス内容はどうでしょうか?
質問に丁寧に答えられるかどうか。
費用についてきちんと説明してくれるかどうか。
また、あなたの要望を受け入れてくれるかどうかも
重要な判断ポイントになると思います。
どんなオプションがあって
どのような費用が掛かるのかなども説明してもらうとよいでしょう。
内容をしっかり説明しないままに、ワンランク高いものをすすめるばあいは
注意が必要かもしれません。
いずれにしても、丁寧に誠実に対応をしてくれるかどうかが
判断材料になると思います。

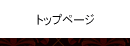
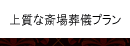
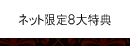
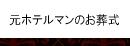
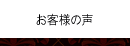
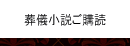
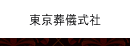
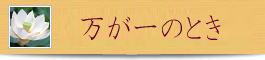
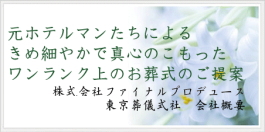


最近のコメント