‘お葬式の基礎知識’
お葬式のときの髪型について
お葬式の時の髪型についてのお話をします。
お葬式では、喪服を着用し、アクセサリーも控えめにするのが普通です。
長い髪は下ろしていると華やかな印象を与えがちです。
パーマヘアの場合も、同じことが言えます。
ですから、一つに束ねたり、まとめたりすることをお勧めします。
華美にならないように、
しかも乱れた感じにならないようまとめるとよいでしょう。
ご焼香やお辞儀をする場面がありますので、その際に邪魔にならないようとの
配慮もあります。
また、髪は低い位置でまとめるのが普通です。
供養事は低い位置、お祝い事は高い位置という常識があります。
また、もし、髪飾りを付ける場合には光沢がないもの、革製品以外の、
黒基調のものを選びましょう。
前髪が乱れがちのときには黒いピンできちんと止めるとよいでしょう。
いずれにしましても、華美でなくきちんとした形で、
控えめな髪型を心がけるべきです。
お葬式のお花 ご供花について
お葬式でお花を贈りたいという時のお話です。
お葬式は急なことが多く、なかなか経験することではないため、
どうしたらいいのかわからないかと思います。
実際、お葬式にお贈りするお花はどの程度のお値段が普通なのでしょうか?
基本的には、5000円程度のお花をお送りすればよいでしょう。
金額は、地域性、会場の様子、また、故人とどの程度親密だったのかなどにより、
若干変わってきます。
相場としましては5000円から1万円を見ておけばよいと思います。
また、若い方でしたら3000円ということもあります。
お花は、一人で送ることもありますし、また、何人かのご友人と一緒に贈ってもよいでしょう。
その際にも、1人3000円から5000円を目安にしましょう。
お花は、お葬式の場所が、斎場などの場合は、直接電話を掛け、
お花を贈る旨伝えることで、手配をしてくれることが多いです。
代金については当日払いができるかどうかを確認しておくと安心です。
お花の種類は、白い色が基調です。
百合、デンファレ、菊、カーネーションがよく使われるお花です。
また、すこしお金が高いですが、胡蝶蘭を使う場合もあります。
故人好きだったお花をアレンジにするということもあります。
いずれにしましても、お花屋さんに「お葬式のお花を」と伝えておけば、お任せで大丈夫です。
葬儀保険について
葬儀の際にはさまざまな費用が必要です。
例えば、祭壇、会館使用料などの
ご葬儀そのものにかかる費用。
また、接待に飲食をすることから、それに伴う費用、
宗教者(お坊さんや、神官)への謝礼の費用。
ほかにも入院をしていた場合にはその清算も必要になりますし
家財の処分や自宅の清掃、その他いろいろなことに、
それぞれ費用が掛かってきます。
また、お墓や仏壇の購入にもお金が必要です。
実はこのお葬式にかかわる様々な費用が遺族にとっては大きな負担になることが
少なくありません。
そんなときのために、葬儀保険が存在します。
葬儀や葬儀にかかわる費用その他を支払うためにかける保険です。
多くは、死亡保険、医療保険の形になっています。
葬儀保険として適しているものは、
「少額短期保険」です。
高齢者でも加入ができ、健康告知項目が減ったことで比較的加入しやすいです。
こどもを連れてお葬式に参列するとき
あなたに小さなお子様がいらっしゃるときに、
お葬式に参列するようなこともあるかと思います。
その時の注意点などをお話します。
ご存知かとは思いますが、お葬式の時には私語を慎みます。
また、読経中は正座をしているのが普通です。
お経を読んでいる間は、焼香意外で席を立たないようにしたいものですね。
けれど、小さなお子様には、長い時間静かにしているということが
難しく、
騒いでしまったり、周りの方々へのご迷惑になることも考えられます。
そのような時は、お子様を連れて静かに席を立ちましょう。
会場の外へ連れ出して、落ち着くまで待つというのが良いのではないでしょうか?
また、焼香をされるときは
どなたか代わりの方にお子さんを見ていていただけばいいです。
いずれにしましても、参列されている方々へ、
迷惑ににならないような配慮が必要になります。
こころにとめておきましょう。
お悔やみの言葉 気を付けるべきこととは
お葬式に参列する際、喪主やご遺族にお悔やみの言葉を述べるという場面が
有ることと思います。
その時に、どのような言葉をかけていいものかと、考えてしまうのではないでしょうか?
お悔やみの言葉は故人とあなたとの関係がどのような形であったか、ということにもよります。
受付では、控えめな声で「このたびは御愁傷様でした」と一声かければよいでしょう。
「この度は突然のことで、とても驚きました。
ご家族の皆様もお辛いことでしょう。」
「○○様には、生前大変お世話になりました。」
など、手短に述べましょう。
また、会社を代表して参列するような場合は、
「この度は御愁傷様でございました。
・・株式会社を代表しまして、ご遺族の皆様に心よりのお悔やみを申し上げます」
と述べればよいです。
お通夜の席ではこのような形でお悔やみの言葉を述べますが、
葬儀では、喪主や遺族にお悔やみの言葉を述べない、というのが礼儀とされています。
目があった場合には黙礼をする程度にするとよいでしょう。
喪中のときに避けるべきこと
喪中のときには、結婚式などのお祝い事への出席は控えます。
また、神社などへの参拝もつつしみます。
故人の冥福を祈る期間であるためです。
結婚式に関しては、最近では百箇日が過ぎている場合には、
出席することが多くなっているのですが、
基本的には慶次への出席をしないようにします。
喪中のときに年を越す場合、
正月のお祝いを控えます。
例えば、門松やしめ縄、鏡餅、などの正月飾りをしない。
おせち料理で新年を祝うことを控える。
また、お年始まわり、新年のご挨拶へ出かけることも
慎みます。
また年賀状は送らないのが普通です。
前年の12月初旬までに喪中はがきを送って、新年のあいさつをしない旨を
伝えておきます。
喪中のご挨拶 (年賀状欠礼の挨拶状)について
身内に不幸があった場合、年賀状を控えるのが普通です。
喪に服するという意味があります。
そのため、
前年に年賀状をいただいている方には、
年賀状欠礼のご挨拶のはがきを出すのが礼儀です。
喪中のご挨拶はがきの形で送ります。
喪中のご挨拶状の文例
父○○が逝去いたしました。
喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます。
本年はひとかたならぬご厚情に賜り厚く御礼申し上げます。
明年も変わらぬ御交誼のほどお願い申し上げます。
当社では、インターネットで、ご葬儀をお申込みいただいた方には、
お名前、ご住所の印刷済みの喪中はがき100枚を無料でお作りしています。
詳しくはこちらをご覧ください。
お葬式での遺族代表挨拶
葬儀、告別式の式次第の中で、
弔電奉読の後に遺族代表のあいさつがありあす。
これは、遺族の代表、もしくは、世話役の代表、葬儀委員長が、
参列者へ挨拶を行うものです。
一般的に、遺族代表のあいさつでは、
このような流れで文章を組み立てるといいのではないでしょうか。
1、ご会葬のお礼
例)本日はお忙しい中、父○○の葬儀にご会葬下さり、誠にありがとうございます。
大勢の方々にお見送りいただき、故人もさぞ喜んでいることだろうと存じます。
2、今後のお願い
例)残された私たちはまだまだ未熟でございます。
今後とも故人同様、ご指導ご鞭撻賜りますようお願いいたします。
3、改めてお礼
例)本日はありがとうございました。
例)短いですがご挨拶とさせていただきます。
この中で、家族や親しいものから見た、故人の思い出、エピソードなどを交えて
挨拶するとよいでしょう。
精進落としについて
精進落としについてお話します。
身内が亡くなった場合、遺族は四十九日までは肉や魚を食べてはいけない、
というしきたりがありました。
仏教の教えの一つ「殺生の戒をおかさない」ために、
肉や魚を食べないようにし、故人の供養をしていました。
そのためにあるのが「精進料理」です。
忌明けまでは精進料理を食べ、忌明けのときに普通の食事に戻る、
それが「精進落とし」です。
現在では、精進落としは、
僧侶や、参列者、また、葬儀の世話役の労をねぎらい、おもてなしをするために
葬儀当日に行われることが多いです。
料理も肉、魚を用いたものが出されるため、
本来の「精進落とし」とは意味が異なってきています。
精進落としでは、喪主の挨拶、世話役の挨拶、
そして僧侶の話があり、
そのあとに食事が始まるというのが一般的ですが、
こうしなければならない、という決まりはありません。
喪主や遺族は、席を立ち
一人一人の席を回って丁寧にお礼を言うとよいでしょう。
葬儀後の精進落としは一時間~二時間ほどで、
最後の喪主によるあいさつで締めくくりです。
仏壇について
お葬式を終え、四十九日や一周忌の際に仏壇をご購入になる方が多いです。
仏壇には故人をしのぶ場、また供養する場としての役割があります。
そして、法要やお盆の際に、宗教的な儀式をする場にもなる、大切なものです。
どんな仏壇を購入したらいいのか、種類、形式は、宗派ごとに地帯ます。
お値段も幅広いのでどうしたらいいのか?と
迷ってしまうかもしれません。
いずれにしても、故人の信仰と予算をしっかりと考えて、購入されることをお勧めします。
仏壇には、花立、香炉、燭台を必ず用意しなければなりません。
この3つを合わせて、三具足と呼びます。
さらに、ご飯を備えるための仏飯器や添え物をのせるための高杯や
鈴があればいいですね。
御本尊は宗派ごとに違いますので、菩提寺に相談なさるとよいでしょう。
少し前までは、どの家庭にも仏間がありました。
そして法要も、自宅で行うことが多かったです。
昨今は住宅事情にもよりまして、特別に仏間を設けることが
できない場合もあります。
そういった時には、
リビング、ダイニング、など家族が集まる場所に仏壇をおくのがよいのでは?と
考えます。

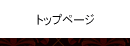
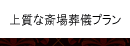
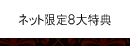
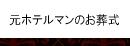
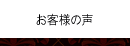
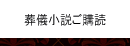
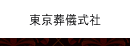
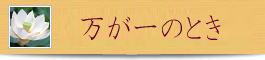
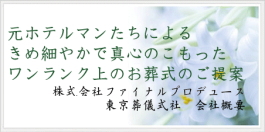


最近のコメント