‘お葬式の基礎知識’
お墓について
お墓を建てるのは、亡くなられてから何日以内・・などという
決まりはありません。
葬儀後にお墓を建てるのでしたら、四十九日や一周忌、三回忌、など
法要に合わせて、というケースが多いです。
先祖代々の墓地がある場合は、四十九日までに建てることが一般的です。
また、生前、購入していた場合も同じくです。
墓地がまだ、定まっていない場合のご遺骨ですが、
自宅に安置したり、また、菩提寺で預かってもらったりします。
お墓は、ただ建てるだけではありません。
お墓がに新しい墓石が据え付けられてから、
開眼法要を営みます。これによって、墓石が宗教上のお墓になるとされています。
お墓は、故人やご先祖様をしのぶためのよりどころ、となる場所です。
ゴミを取り除いたり、周囲を掃き清めたり、など、
常に清潔にしておきたいものですね。
お供えには、故人が好きだったものを備えるのが普通です。
お彼岸のお墓参りについて
お彼岸は、春分の日、秋分の日を中日にして、
前後1週間のことを言います。
そもそも、お彼岸とは何かと言いますと、
あの世への入り口にある三途の川の向こう岸のことです。
祖先が無事に、あちら側、彼岸へ渡ることができますように、
と、願って供養を行うのです。
彼岸は1週間ありますが、
最初の日を「彼岸の入り」と呼びます。
最後の日は「彼岸の明け」と言います。
お彼岸のお参りには、花やろうそく、線香などを持って行きます。
彼岸という行事は、他の仏教国にはありません。
日本独特のものです。
この背景には、、種まき、収穫の時期でもあることから、
自然や、ご先祖様に感謝の念を抱き祈る、
そのような気持ちにつながり、大切な行事とされるようになったようです。
新盆について
亡くなった後に初めて迎えるお盆のことを、「新盆」といいます。
お盆の呼び名は、正式なものでは「盂蘭盆」です。
地域によって違いますが、普通は8月の13日~16日までの間を
「盆」と呼びます。
この期間は、先祖の霊を迎えて供養しましょう、ということです。
特に新盆は、初めてのお盆ですから、手厚くしっかりと供養します。
忌明けの前に新盆を迎える、という場合がありますが、
この時は、翌年にすることが多いです。
家庭の判断で、その年のうちに済ませる場合もあります。
新盆では、盆棚を設けて、位牌を仏壇から出しておき、
生花やお供物を備えます。
提灯も灯します。
親戚、近親の方々。友人を招いて法要を営みます。
僧侶に読経をしていただきます。
その後は精進料理などで、おもてなしをします。
新盆の法要のときは、
喪服を着るのが普通です。
お年忌について
四十九日の法要を終えると、葬儀後の慌ただしさは少しずつ消え、
落ち着きを取り戻します。
その後は、亡くなった方の追善供養として、
1年、3年、7年、13年、17年、23年、27年、33年、というように、
3と7のつく年に年忌法要を行います。
一周忌は、亡くなった年の翌年に営まれます。
初めての命日の法要です。特に重要な年忌法要です。
三回忌は、一周忌の翌年に営まれます。
これから、3年目を迎える、という意味です。
命日から数え、満6年目に営むのが7回忌、
と、いうふうに行います。
一般的には三十三回忌で終わります。
地方や家によって、五十回忌を行い、回忌を終えるところもあります。
「とむらいあげ」と言います。
また、例えば、祖母と祖父、など、
祖先の年忌が重なった場合には、命日の早い方に合わせて、
法事を行っていきます。
合わせて行うことを「併修」と呼びます。
四十九日の法要
仏教では、命日から数えて七日ごとに法要を行います。
中陰法要です。
初七日、二七日、三七日、・・・と続き、忌明けの前に行う、七七日が、
四十九日です。
初七日は、葬儀後にそのまま済ませることが一般的になっています。
葬儀後の初めての大きな法事として「四十九日の法要」があるのです。
これは、従来は、ご自宅や、また菩提寺で行うことが多かったのですが、
最近では葬儀社の式場で行うことも増えています。
四十九日の法要に必要な準備を時系列にリスト化してみましたのでご確認ください。
法要の前には、菩提寺のご住職と連絡を取り、日取りを決めます。
四十九日とはいいますが、親戚が集まりやすいように、
四十九日の直前、土日を利用する場合がよくあります。
また、日程が決まったら、親類縁者に連絡を取り、参加する人数を決めます。
四十九日の後には、会食をするのが一般的なため、
そのための式場や、仕出しを注文しておきます。
また、手土産も用意します。水引をつけ、表書きは「志」「粗供養」と書きます。
読経をしていただく、お坊さんへは挨拶と謝礼をお渡しするため、
その準備も必要です。
四十九日が終わりますと、白木の位牌から漆の塗り位牌に変わり、仏壇に収めます。
そのため塗り位牌と仏壇の用意が必要となります。
還骨葬とは
ご葬儀の一般的な流れとしましては、
ご臨終のあと、葬儀社へのご連絡をいただき、
ご自宅に安置、その後、
納棺、お通夜、葬儀・告別式、出棺、ご火葬、後飾りとなります。
ですが、ご事情により、ご火葬のみのお葬式、いわゆる
火葬式を選択なさる場合もあります。
還骨葬とは、火葬式をされたあとに、
ご自宅にお骨を安置し、お坊さんに読経をしていただく様式です。
費用をかけての一般的なお葬式をお望みでないご遺族の、
お葬式の形です。
ご自宅にお骨を安置し、お経をあげていただくことで、
それを別れの儀式とする、という考え方。
通常のご葬儀に比べますと、葬儀に掛かる費用を抑えることができること、
お身内だけでひっそりとお送りすることができることが、利点です。
還骨葬について、詳しくお聞きになりたい場合は、
フリーダイヤル0120-00-5943へお電話いただくか、
または、下記よりメールにてお問い合わせください。
形見分けの意味とその方法
形見分けとは、故人と親しかった人たちが
故人をしのび、思い出すために、遺品を贈る習わしです。
形ばかりではなく、遺品を贈られて心底喜んでくださる方に
お渡ししたいものですね。
故人との関係、親交が深さと、好みなどに合わせて
考えるとよいのではないでしょうか?
形見分けは四十九日を過ぎてからおこないます。
故人が愛用していた、衣類ですとか、アクセサリー、メガネなど、
また、家具や小物を送ることが普通です。
衣類はきれいに洗います。
クリーニングに出してもよいでしょう。
小物ならば、汚れを落としてきれいにしましょう。
形見分けは故人から見て目上にあたる方々には、しないのが普通です。
また、「この品をこの方へ」という形の遺言がある場合には、
それを考慮するとよいでしょう。
形見分けの品を渡すときは、贈り物の形で箱に入れません。
薄い紙で包んで「遺品」などと表に書き、直接お渡しするようにします。
一つ注意が必要なことは、
高価な品物を贈るときです。
たとえ形見分けであっても、その品が高価なものだった場合は、贈与税がかかってしまう場合があります。
ですから、高価なものを贈る場合は、先方のご迷惑や金銭的な負担にならないように、
配慮が必要です。了解を得て、贈るのが望ましいです。
香典返しについて
仏式の場合、香典のお返しは四十九日後、忌明けの報告とともに、
お礼をする意味がありました。
しかし、今は葬儀の葬儀の当日に受付で、そのままお渡しすることが大半です。
この場合の香典返しは、半返しと呼ばれます。
香典をいただいた額の半分を目安にした品を、お礼を添えて渡すのが普通です。
お香典返しは、葬儀の時にいただいたお香典へのお礼の意味がありますので
心を込めてお返しするようにしましょう。
お香典返しは、
タオルやハンカチ、緑茶、またせっけんやコーヒーセットなどの
日用品が主流です。
故人を思い出してしまわないように、との配慮から、
印象に残るような品物を渡さないのが普通です。
弔事に使う熨斗に「志」、喪主の姓名を書いて渡します。
香典返しも葬儀プランに含まれている場合もありますので
葬儀社に相談してみるとよいでしょう。
葬儀後にすべきこと
ご葬儀が無事に終わり、ほっとしている間もなく、
するべきことはたくさんあります。
お骨を安置した部屋は、忌明けまではそのままに、
ほかの部屋を片付けます。
葬儀の後は、不幸を後で知ったという方が弔問に訪れる場合もありますので、
華美な飾りなどは控えておきます。
仕出し屋などで借りた食器類は確認して返却します。
また、道案内や、表示板も片付けていきます。
葬儀の翌日には、遺族、近親者とともにお寺に参り、
お経をあげていただきます。
もし、お通夜、葬儀当日にお布施を渡していない場合には、
この時に渡すとよいでしょう。
金額は規定がある場合もありますが、
ない場合には葬儀社に聞いての情報や、
檀家総代に聞くなどして決めます。
また、戒名に関するお礼も渡しましょう。
葬儀社からは、葬儀終えて2~3日たったころに
請求書が届くことと思います。
明細の内容と金額を確認し、指定された方法で支払いを済ませます。
遅くとも1週間以内には済ませるようにしましょう。
葬儀でかかったものの領収書は、
遺産相続での相続税の控除の対象にもなりますし、
正確に細かく記載し保管しておきましょう。
お寺へのお礼でも、領収書が必要なことを告げ、書いていただくことをお勧めします。
環骨勤行とは
環骨勤行(かんこつごんぎょう)、という言葉をご存知ですか?
聞きなれないという方が多いのではないでしょうか?
還骨(かんこつ)は、故人が火葬を終えて、
骨に還りましたよ、という意味です。
骨に還った故人を、後飾り祭壇のあるところまで、
お迎えする時行われるのが「環骨勤行」です。
この儀式は自宅にて行います。
火葬場でだびに付された後、
帰宅し、僧侶にしていただきます。
僧侶の読経が流れる中で、参列者は焼香をしていきます。
(僧侶は不在で、焼香のみという場合もあります。)
後飾り壇には、遺影、位牌、線香、ろうそくを置き、
供花やお供物も用意します。
後飾りの用意につきましては、
火葬場を霊柩車が出発した後に世話役がすることになりますが、
葬儀社に任せることもできます。
« Older Entries Newer Entries »
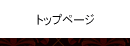
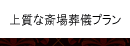
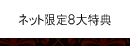
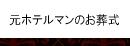
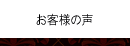
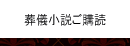
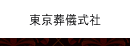
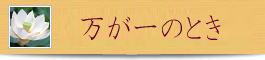
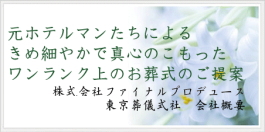


最近のコメント