‘お葬式の基礎知識’
骨あげについて
骨あげは、火葬が終わった後に、遺族親族が炉の前に集まって行います。
収骨式、拾骨、骨拾い、という言葉でなじみがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
骨あげは、喪主から行い、続いて、遺族、近親者、友人知人という順番で行います。
故人との関係が深い順番と覚えておくとよいでしょう。
骨あげは、竹の箸を使います。
2人1組で両側から一つの骨を挟み、骨壺に入れます。
その後は次の方へお箸を渡します。
この形で、みなで骨を拾います。
この時もし、落としてしまっても、
「もう一度お願いします」といい、やり直せば大丈夫です。
全ての骨が骨壺に収まったら、最後に喉仏を喪主が拾います。
これはなぜかと言いますと、喉仏には仏様が宿っている、と言われているためです。
形が、仏様が座っている様子に似ているからだと言います。
そのあと骨頭が箱の上部に収められ、骨あげは終わりです。
火葬場スタッフにより骨壺は白木の箱に入れられ、布でくるんで渡されます。
火葬・収めの式について
仏式のご葬儀・告別式が終わり、出棺を終えた棺は、
火葬場へと向かいます。
火葬場へは遺族、親戚、そして故人とごくごく親しい間柄の方が行くのが普通で鵜s。
当日になって、同行したいという方がいらっしゃれば、
一緒に行っていただくこともできます。
霊柩車には、棺と葬儀社のスタッフが乗り込み、その後ろから喪主をはじめとする
遺族が乗った車が続いていきます。
霊柩車には喪主が一緒に乗る場合もあります。
霊柩車、タクシー、ハイヤー、マイクロバス、の順で車が並び、
火葬場へと向かいます。
火葬場についたら、棺は霊柩車から降ろされ、
炉の前に安置されます。
ここでは火葬許可証が必要になりますので、忘れずに持って行きましょう。
葬儀社で提出してくれる場合があるのでその点は、相談されるといいと思います。
炉の前には机があり、
位牌と遺影を飾ります。
ここで行われる儀式が「収めの式」です。
僧侶の読経が流れる中、棺が炉に収められていきます。
喪主、遺族、親族という順番で焼香し、合掌をし、火葬が始まります。
火葬は1時間ほどかかります。
遺族や親族は控室で待ちます。
葬儀社によっては控室でお菓子やお酒を用意してある場合もあります。
故人の思い出話などをしながら待つと、供養になります。
仏式葬儀での出棺
仏式葬儀での出棺についてお話します。
ご自宅、または斎場にて、
大切な方のためのお通夜を行い、告別式と続いて、
いよいよ出棺となります。
ご自宅でご葬儀を出された場合には、住み慣れた家との最期の別れとなる儀式です。
最後のお別れとして、
遺族や、近親者の皆さんで棺を囲んで、お花を入れていきます。
祭壇や棺の回りに飾られていた、たくさんのきれいな花で
故人を飾ってさしあげるのですね。
この時が故人に触れることのできる最期のときとなります。
十分にお別れをしてください。
そしてお花を入れ終わった後に、棺にふたをし、
くぎ打ちの儀式を行います。
石で、棺のくぎをうつ儀式です。
「石で打つ」ということにも意味があります。
これは、死者がわたるとされる三途の川の河原の石という意味があり、
三途の川を無事、何事もなくわたって、浄土へたどり着きますように、との願いがあるのです。
くぎ打ちが終わりますと、出棺になります。
喪主は位牌を胸に、先頭に立っていきます。
そして故人と血縁の深い者が遺影を持ちます。
そしてその後ろに棺が続くことになります。
棺は男性の近親者で持ちます。
出棺に際し、喪主はお見送りの参列者に頭を下げてご挨拶をします。
霊柩車のクラクションとともに、出棺となります。
お見送りの人は合掌して見送ります。
家族葬について
家族葬とは、身近な家族、身内だけで行う小さな規模のお葬式です。
基本は家族のみですが、親戚、また故人と生前親しかった友人が参列する場合もあります。
この「家族葬」という名前が使われ始めたのは1990年代です。
核家族が増えたことがその背景にあるようです。
はじめは、一般的なお葬式の中の「規模の小さいご葬儀プラン」との位置づけだったのですが、
最近では、すこし形が変わってきています。
大切な人を送るための、ごくごく親しい身内や友人とともに、
ゆっくりとした心温まるご葬儀を望む方々が、「家族葬」の形を取ることが多いです。
密葬にルーツがあるとも言われていますが、密葬の場合は遺族だけでお別れをして火葬をし、のちに本葬式をするというもの。
家族葬の場合は、お通夜、告別式をともない、遺族だけでなく親戚、ごく親しい友人も参列し、
火葬場まで行くというかたちです。
弊社でも、美しい花祭壇で、こころあたたまる家族葬のプランがございます。
ご予算に合わせて、お値段以上のサービスをしています。
プランの一例>>家族葬50
葬祭業者の種類
突然のご不幸により、お葬式を行うことになったとき、
葬祭業者の存在は不可欠だと感じます。
けれど、葬祭業者と一口に言いましても、それがどんなものかご存知ですか?
葬祭業者には3つの種類がございます。
まず1つ目。
弊社のような「葬儀社」または「葬儀屋」と呼ばれるものです。
いわば、専門の葬祭業者です。
私たちの仕事は、葬儀全般です。
お葬式は、ギフトの会社、仕出し業者、霊柩車会社、など
複数の業者が協力して行います。
このさまざまな業者を取りまとめる役割を持つのも葬儀社です。
費用はまず、葬儀社でほかの業者への支払いを立て替え、
後にご喪家に請求するというのが普通です。
葬儀社も、全国規模の大きなところもあれば、
家族でこじんまりと経営しているところまで様々です。
2つ目は「互助会」という葬祭業者です。
積立金を集め、それをもとにして葬儀を行います。
互助会、という名前ですが、民間の営利団体です。
ですから、せっかく積み立てていても、その会社が倒産してしまうこともあります。
この場合積み立てたお金の半分ほどは戻ってくるのですが、すべてではありません。
この点に注意が必要で、互助会に入る場合はその経営がどうなっているのかを知り、判断するといいのではと感じます
また、積立金があれば、葬儀にかかる費用はすべて賄うことができるか、といえば、
そうとは限りません。
どの範囲まで、賄えるのか、確認しておくとよいでしょう。
最後に、「JA」「生協」など、組合員を対象にした葬祭業者です。
基本的には、組合員のためのものですが、JAに関しましては組合員ではなくとも、葬儀を行うことができます。
葬祭業は、許認可がいらない業界です。
ですから比較的新規参入がしやすいので、さまざまな業者が存在します。
納得のいくご葬儀を行えるよう、知っておくとよいですね。
数珠について
数珠は、お通夜の時にも、できるだけ持っていきます。
数珠はもともと、お経を読むときに、何回唱えたのかを数えるためのものです。
珠の数は108個あるのが正式な数珠です。これは煩悩を表しています。
短いものの場合は、左手の親指にかけるようにして持ちます。
長いものは、両手の中指にかけます。このとき房が真ん中に来るようにします。
合掌の時は、もったまま手を合わせます。
数珠は必ず手に持ちましょう。
椅子や畳の上に置くことは、絶対に避けましょう。
お香典について
お香典についてお話しします。
お通夜、告別式に参列することになって、お香典はどうしたらいいのかしら?と、疑問に思うことがおありでしょう。
そもそも、お香典は、線香やお花の代わりに霊前に供えます。
もともと、故人にお花を供えていたのですが、現在では現金を包むようになりました。
不祝儀用ののし袋に現金を包んで、お通夜またはお葬式のどちらかで持参するものです。
その金額は故人とのかかわりによって変わってきます。
ただし、4、9、という金額は「死」「苦」を連想させるため、タブーです。
お香典は不祝儀袋に入れて、袱紗もしくはハンカチで包んで持っていきます。
死の予測してあらかじめ準備していた、と思われてしまうことを避けるため、新札を包まないようにします。
もし、手元に新札しかなかった場合には、折目を付けて包みます。
表書きは薄墨で書きます。これは涙で墨が薄まったという意味があります。
仏教では、「御霊前」「御仏前」「御香典」
キリスト教では「献花料」
神道では「御玉串料」「御神前」と書きます。
お札が2枚以上になる場合は、お札の向きをそろえます。
不祝儀袋の中包みは、上側を下側にかぶせるように重ねましょう。
祭壇に供える際は表書きを自分の方向に向けておきます。
受付の場合は受け取る人に向けて渡します。
火葬式について
火葬式についてお話しします。
火葬式というのは、通夜・告別式を行わずに火葬のみを行います。
一般的なご葬儀の流れでは、ご逝去された後、故人様をご自宅(もしくは斎場)まで搬送し、
通夜、通夜振る舞い、告別式、火葬、精進落とし、という流れで行われます。
火葬式では、ご逝去後、故人様を火葬場に搬送し、火葬の流れとなります。
出来るだけご葬儀を質素に、という故人様の遺志がある場合や、
後日、しのぶ会を開かれるためにご火葬をするなど、様々なお考えの方がこの形を取られます。
火葬式の場合、費用を抑えることができる点がメリットですが、
お通夜や告別式というお別れの儀式を行わないため、心行くまでお別れをする時間がありません。
弊社のご火葬プランでは、火葬場にてお別れのお花入れをしていただき、
お別れとなります。
費用をできるだけ抑えたい、けれどお別れの時間はできるだけとりたい、
そのようなお考えであれば、家族葬をおすすめいたします。
ご焼香のマナー
仏式では、お通夜、ご葬儀、法事の際、必ずご焼香を行います。
ご焼香とは、香をたくことによって、仏前を清める役割と、そのお香を霊への手向けとする意味合いがあります。
ご焼香の儀式は、お釈迦様が生きておられた時代から続いてきた儀式です。
多くは抹香をたくかたちで行われます。
ご焼香の一般的な流れは、
1)ご焼香台の手前で遺族にと僧侶に向かって一礼します。
2)焼香台の前に進んだら、遺影を仰ぎ、一礼。そして手を合わせます。
3)ご焼香の時は、手に持っていた数珠は左手にかけます。
抹香は右手で、親指、人差し指、中指の3本の指でつまみます。
4)抹香をつまんだら、右目の高さまでおしいただきます。掌は返しません。
5)抹香を香炉のなかへと静かに落とします。
6)遺影をもう一度仰ぎ、手を合わせます。そのまま下がって、遺族に一礼します。
宗派によっては抹香をくべる回数が違います。
ご遺族やまわりの方々のされることをよく見て、同じようにご焼香すればいいのではないでしょうか?
キリスト教のお葬式
キリスト教のお葬式についてお話しいたします。
キリスト教では、仏式で言うところのご焼香が、「献花」の形になります。
お香典の呼び名も、カトリックの場合は「御ミサ料」、プロテスタントの場合は「御花料」です。
キリスト教式のお葬式に参列する場合、数珠などの仏式のものは持参しないようにしましょう。
また、讃美歌、聖歌を歌う場面がありますが、知らない場合には静かに聞いていればいいのです。
献花の方法ですが、
まず、花が右手側になる様に受け取ります。
そして祭壇まで進んで一礼。
その後、花の向きが手前になるように時計回りに回します。
右手に持っていた手を左手に持ち替え、花の根元の部分が祭壇側になる様に捧げます。
最後に遺影に向かって一礼します。
参列する時の服装は男性は、喪服や、濃い紺色などの暗い色のスーツを着用しましょう。
女性の場合は、喪服、そのほかに、色味やデザインが地味目のワンピースなどがよいでしょう。

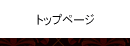
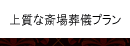
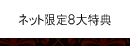
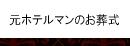
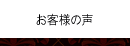
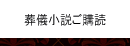
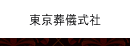
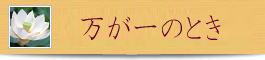
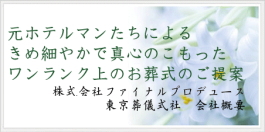


最近のコメント